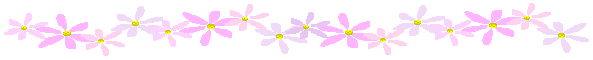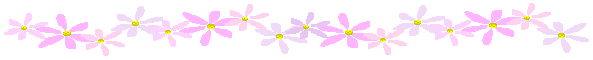
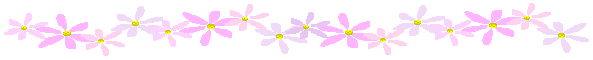
風呂上がりにと拝借してきたビールを片手に開いたドア。
「飲むか?」
声をかけて見たものの、返事はない。
近付いくと、ソファに転がったままアリスはすーすーと心地よい寝息をたてていた。
「…おやおや…本当にお疲れだったんだな…センセイ」
そりゃそうかもしれない。およそアウトドアには縁のないと思われるアリスのこと、いくら捜査のためとはいえ一日山の中をあちこちと動きまわったら疲れるのは当たり前。止めとばかりに最後にはGWということもあって家族連れで賑わうピクニックセンターのオリエンテーリングコースを行ったのだから。
「とんだ連休だったなぁ…」
ま、おかげで犯人の目星はついたけど…。苦笑しつつ伸ばした指で柔らかな髪を梳く。
アリスの一部に触れる。
それだけで愛しさが込み上げてくる。
優しい想いに癒されて、疲れが消化されていくようだ。
ふわり…絡んだ髪に唇を寄せると、鼻腔をくすぐるしみついた太陽の匂い。
「…おっと…白髪発見…」
自分程ではないけれど、最近アリスの髪にも時折白いものを見かけるようになった。
一本、二本程度のそれを目くじらたてて抜いているらしいけれど。
「何を苦労してるんだ? …ってもう、それも当然の年かな」
三十も半ばだ。普通に考えれば人生の折り返しあたりには来ている。
「…でも、まだまだ学生でいけそうだよな…アリスは…」
無防備な寝顔はまるで出会った頃と変わらない。髪から、頬へ指を移す。
…触れるか触れないかの距離でたどるアリスの輪郭。どこもかしこも好きなところばかりだ…。つい、吸い寄せられるように、近付ける唇。
「アリス…」
「…ん……」
ぱちっ…と目が開いた。
「あ…火村…風呂出たん?」
「ああ、ごめん。後からって言ってたけど来なかったから…悪かったな、起こしちまった」
「ん…いや…寝るつもりなかってんけど…」
「疲れてたんだろ」
「…うん。そうみたいや…」
「風呂、どうする? 汗かいてるだろ?」
「…んー、もうちょっと目醒めてから入る」
でないと風呂の中で沈没してまうからと笑うアリスにせがまれてその身を起こしてやる。
「ありがと…」
しばらくそのまま肩に持たれていたアリスが『そうや』と突然、身を正した。
「どうした?」
「聞きたい事があってん」
真面目な顔に覗き込まれて、火村も手にあったビールを机上に置いた。
「なんだよ。急に改まって」
「火村はいつ俺のこと見付けたん? あれが初めてって事ないよな」
「あれ?」
「五月七日の階段教室」
「あぁ、あれ…どうした、唐突に」
「…いやぁずっと聞いてみようと思ってたんやけど、なんか聞きそびれてて。今日こそって思って…」と、指差すカレンダーは今日。
そうか…今日は5月7日…。
「いつだと思う?」
「わかれへんから聞いてるんやんか。こんな好みの顔、もっと前に見てたらもつと早くに気付いてると思ってんけど。どう考えてもそれ以前って…思いつかへんねん」
「そりゃ、そうだ…」
「なんで?」
「だって、アリス…いつも眠ってたからなぁ…図書館で」
「…そう…やったんか。そりゃ気付かへんなぁ、目つむってたら。起こしてくれたらよかったのに」
「あの頃は起こす術を持たなかったからな…」
「今は?」
「ん、さっきの通り」
「…もう一回…して」
くすくすとアリスは笑う。ああ、その笑顔だ…と火村は思う。
寝顔も可愛かったけれど、垣間見た笑顔の方が数倍も素敵だった。
だから、追って…追い求めて…今、ここに居る。
そんな一瞬の逡巡に開いた間をどう受けとめたのか『あかん?』と問われて。
「とんでもない…愛してるよ」
火村は王子さまのキスを贈った。